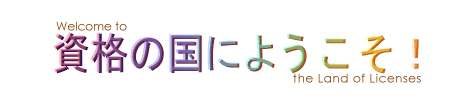仙台初詣合格祈願 司法書士
仙台初詣合格祈願 試験について

ここでは、資格試験の基礎的な性格、役割について解説します。

|
司法試験とは、裁判官・検察官・弁護士になろうとする者に必要な
学識・応用能力を持つかどうかを判定するものである。
日本国憲法は権力分立制を採用し、
権力の均衡と相互抑制で国民の権利と自由が侵害されない体制をとっている。
このうち司法権の運用を担うのが法曹三者・すなわち裁判官、弁護士、検察官である。
|

|

裁判を指揮し、事案に対して法律的判断を行い、判決を下す。
行政権の圧力を排し、司法権の独立を守るため、強い身分保障が認められている。

たとえば強盗・殺人・贈収賄など多くの刑事事件について起訴し、法の正当な裁きを独立して要求する。
刑罰の実施についても監督する。

民事訴訟の代理人として出廷し、依頼人の法律上の利益を弁護したり、
刑事事件では被告人の弁護人として法廷活動を行う。
検察審査会が起訴すべきを起訴しなかったと判断した場合には、
弁護士が検察官の役割を果たすことがある。
法廷外では、法律問題について当事者の相談に応じ、紛争の予防や解決に当たる。
|

|
裁判官や検察官は国家公務員であり、最高裁判所やその他の裁判所、法務省の組織内で仕事をする。
転勤、定年制が定められ、特に検察官は転勤が多い。
定年は裁判官が65歳(最高裁では70歳)、検察官は63歳であるが、
どちらも退官後登録すれば弁護士として活動することができる。
裁判官は、公の弾劾による罷免、(最高裁判所の場合、国民審査による罷免)のほかは
強い身分保障を受け、報酬も法律に規定された特別給である。
なお、検察官は通常3年に1回適格審査を受ける。
検察官適格審査会の議決、余剰の人員によって罷免される以外は
検察官も身分保障が強く、俸給も裁判官に準じて安定している。
一方で、弁護士は民間人で自由業である。
高額所得者の代表格であり、人気のある職業であるが、
実際のところ、不動産関係の受託状況はバブル崩壊以降減少し、
経営が厳しくなっているのも実情である。
年収としては40代で1500万円、50代では2000万円前後のようである。
|

|
司法試験に合格しても、ただちに裁判官、検察官、弁護士になれるわけではない。
司法試験に合格した翌年の4月から2年間の司法研修が始まる。
この期間に、学んだ知識を実際の事件に応用する力を養う。
司法試験に合格すると、身分は国家公務員に準ずる司法研修生として国から給与が支給される。
前期修習(4ヶ月)、実務修習(1年4ヶ月)、後期修習(4ヶ月)に分かれる。
前期修習では実務に関しての基礎的な勉強を行う。実務研修では裁判所、検察庁、法律事務所に通勤して事務を学ぶ。
後期修習は以上の仕上げという位置づけを持つ。
|
次ページ司法試験のすべて

![]()
![]()
![]()
![]()